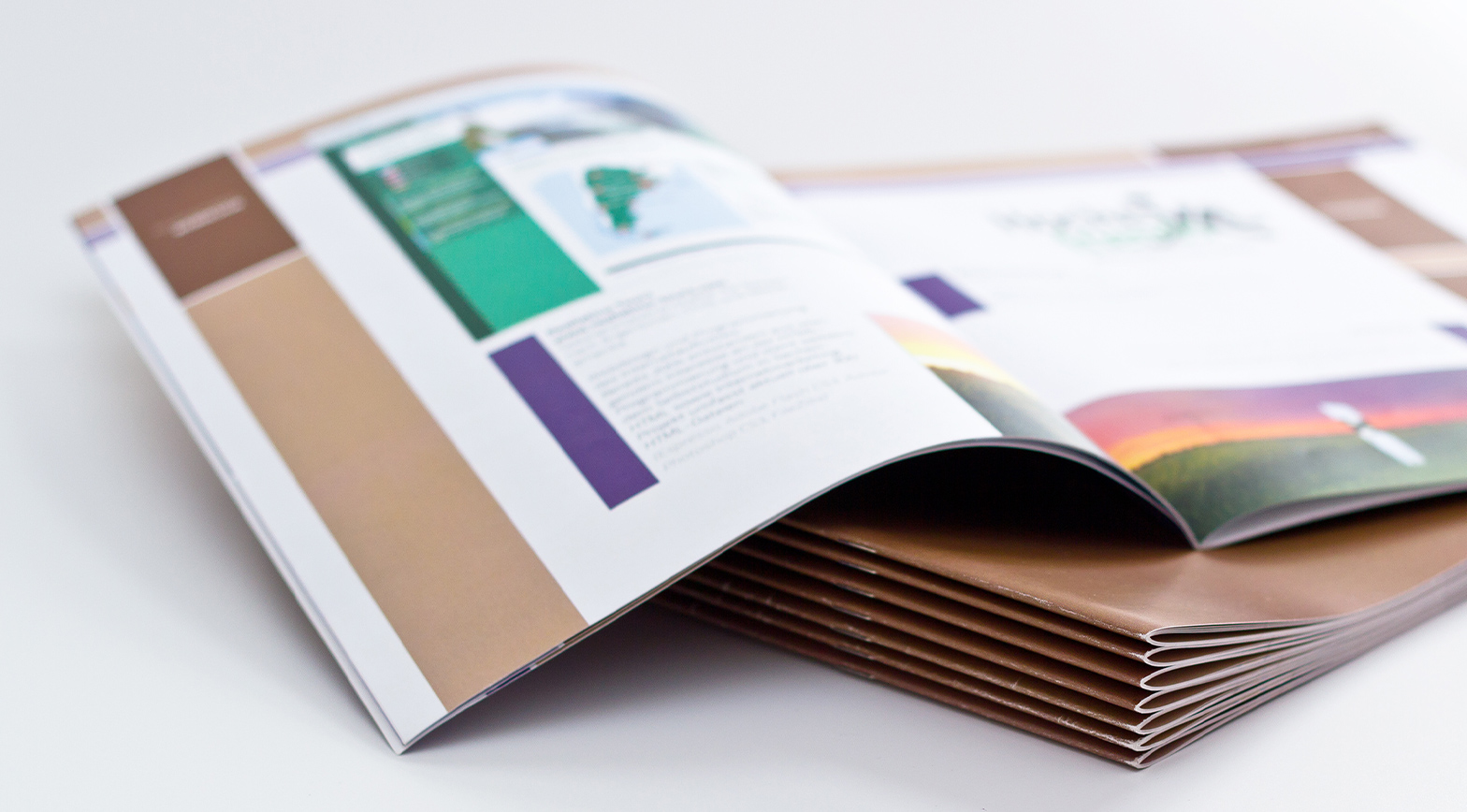記者発表会とは?|記者会見との違いや必要な準備、実施事例についてご紹介!

記者発表会は、企業が新商品やサービスを世の中に広く伝える重要な機会です。しかし、一見すると「記者発表会なんて大企業だけのもの」「自社には関係ない」と思う方も多いのではないでしょうか。 記者発表会は決して大企業や特定の企業だけの広報施策ではありません。どの企業でも気軽に開催でき、さらには費用対効果が高い施策なのです。 本記事では、記者発表会の基本的な考え方から準備の進め方、成功要因、効果測定まで、実践的なノウハウを体系的に解説します。
記者発表会とは
記者発表会とは、企業がメディア各社を会場へ一斉に招待し、新商品や新サービス、おすすめの新規事業などを公式に披露・プレゼンテーションする広報イベントです。最大の特徴は、一度の開催で多数のメディアに情報を届けることで、短期間での爆発的な認知向上と社会的信頼の獲得が期待できる点にあります。
また、単なる情報提供の場に留まらず、記者と対面で接することで、将来的なメディアリレーションズを構築するための極めて重要なコミュニケーションの場でもあります。開催にあたっては、メディア側の利用のしやすさを考慮し、スムーズな案内や運営が求められます。
記者発表会と記者会見の違い
多くの人が混同しがちですが、記者発表会と記者会見の違いは、開催の「目的」と「性質」にあります。
「記者発表会」は、企業が新商品の発売などに合わせ、ポジティブな情報を能動的に発信するPRの場です。一方の「記者会見」は、不祥事への謝罪や社会的な重要事案に対し、世間やメディア側の要請に応じて公式な見解を述べる性質が強くなります。
下記の表にその違いについてわかりやすく記載しておきます。
| 項目 | 記者発表会 | 記者会見 |
| 主導権 | 企業側が主導(自ら発信) | メディア側が主導(社会やメディアに求められて対応) |
| 時間配分 | プレゼンテーション70% + 質疑30% | 説明30%+質疑応答70% |
| 準備期間 | 6週間前〜3ヶ月 | 即日から4週間前 |
| 会場設営 | 演出を重視 | 即時性・姿勢を重視 |
| 指標 | 掲載内容の量および質 | ネガティブ報道の数 |
記者発表会は企業が「伝えたいことを伝える場」、記者会見は「聞かれたことに答える場」と理解するとよいでしょう。
ただし、プロの現場でも記者発表会も記者会見も「会見」と一言でいうこともあるので、テストで出るわけでもないので、そこまでこだわる必要はありません。
それでは、今回は以下に「記者発表会」の役割について5つポイントを挙げておきます。
1.新製品・サービスの認知度向上
新製品や新サービスの発表、事業戦略の転換、企業合併・買収など、企業にとって大きな節目となる情報を広く社会に伝えることが第一の目的です。各メディアに集まってもらい、報道していただくことで、ターゲット層だけでなく、潜在顧客に対しても認知度を効率的に高めることができます。報道露出は、企業の信頼性や権威性を裏付ける効果も期待できます。
2.メディアとの信頼関係強化
記者発表会は、単なる情報提供の場に留まらず、メディア関係者との良好な関係を築くための重要な機会です。質疑応答の時間を設けることで、メディアの疑問に直接答えることができ、透明性の高い企業姿勢を示すことができます。また、発表会後の個別インタビューや懇親会などを通じて、メディア担当者と個人的な関係を深めることで、将来的な取材協力や情報提供の円滑化に繋がります。メディアとの信頼関係は、広報活動の成否を大きく左右します。
3.議題設定:社会的な話題へ波及させるきっかけづくり
記者発表会で発表される内容は、社会的な関心事を喚起し、世論を形成する力を持っています。例えば、環境問題への取り組みや社会貢献活動に関する発表は、企業が社会的な課題解決に貢献していることをアピールし、企業イメージの向上に繋がります。また、業界のトレンドを牽引するような革新的な技術発表は、新たな市場の創出や社会的な議論を巻き起こす可能性があります。このように、記者発表会は単なる情報の告知だけでなく、社会的な議題を提示し、世の中に影響を与える場としての役割も果たします。
4.ステークホルダーとのコミュニケーション
メディアが報じる先にはステークホルダーがいることを忘れてはいけません。記者発表会は、メディアを通して、投資家、取引先、従業員、消費者など、様々なステークホルダーに対して企業のメッセージを伝える場でもあります。企業戦略や事業の方向性を明確に提示することで、投資家からの評価を高め、資金調達を有利に進めることができます。特にスタートアップ企業の資金調達時は大きな役割を果たします。また、取引先との関係強化や、従業員のモチベーション向上にも繋がります。このように、記者発表会は、企業の多角的なコミュニケーション戦略の一環として機能し、最終的には企業価値の向上に貢献します。
5.危機管理(正確には記者会見):透明性のある情報開示によるレピュテーション保護
企業にとって不利益となる事態が発生した場合(例:製品のリコール、不祥事など)、記者発表会は迅速かつ透明性のある情報開示を行うことで、企業のレピュテーション(評判)を守るための重要な手段となります。正確な情報を早期に開示し、質問に真摯に答えることで、憶測や誤解が広がるのを防ぎ、社会からの信頼を失うことを最小限に抑えることができます。危機発生時の適切な情報開示は、企業の存続にも関わる重要な要素です。
記者発表会の準備プロセス

記者発表会の定義と性質を理解したところで、ここからは具体的な開催に向けたステップを解説します。
記者発表会の準備には、会場の手配から資料作成、メディアへの案内まで多岐にわたるタスクが存在します。一般的には開催の3ヶ月〜4ヶ月前から動き出すのが理想的です。限られた時間の中で漏れなく準備を進めるために、まずは全体像となるスケジュールを確認しましょう。
企画段階(開催8-12週間前)
目標設定の具体化をしていきましょう。記者発表会を成功させるには、曖昧な目標ではなく、測定可能な具体的な目標設定が重要です。SMART原則を活用しましょう。
- Specific(具体的):「日経新聞の掲載を獲得、WBSでの放送」など明確な目標
- Measurable(測定可能):来場メディア数、掲載記事数などの数値目標
- Achievable(達成可能):現実的で実現可能な目標に調整
- Relevant(関連性):企業メッセージやブランドとの整合性の調整
- Time-bound(期限明確):プロジェクトマネジメント、スケジュール管理
目標とするべきターゲットメディアを選定する
次に招待したいメディアをリストアップして、分類し、優先順位をつけましょう。
下記の表はあくまで例ですが、発表内容に応じて、招待するメディアの優先度が変わることを覚えておきましょう。
| 媒体分類 | 影響力 | 専門性 | ターゲットへのリーチ | 優先度 |
| 全国紙 | 高 | 中 | 高 | B |
| 業界紙 | 中 | 高 | 高 | B |
| Web媒体 | 高 | 中 | 中 | A |
| 経済番組テレビ | 高 | 低 | 高 | A |
ここで重要なことは、情報伝播設計です。つまり、どのメディアが発信すればその後メディアの報道が続くのか?(報道連鎖)を考えておくべきです。
例えば、Webメディアの報道露出量が増えれば増えるほど報道連鎖が起こりやすくなるというデータもあるため、まずはWebメディア媒体を優先的に呼ぶ、その他、同じ系列、例でいえば、読売新聞などに掲載されれば、翌朝の日テレの情報番組「ZIP!」などで「新聞読みコーナー」で取り上げられる可能性も上がります。このように様々な可能性を広げる、また費用対効果を高くするためにもメディア選定についてはじっくりと考えるべきです。
準備段階(開催6週間前)
効果的な会場選定
会場選びは参加率に大きく影響します。以下の4つの要素を総合的に検討しましょう。
- アクセス性:主要駅付近やアクセスの良い会場だと参加率が向上
- コスト効率:予算に対する設備の充実度
- 機能性:必要設備(音響、映像、Wi-Fi等)の完備
- 適合性:発表内容とのイメージ整合性
推奨する会場タイプは以下の通りです:
- 主要駅近くのイベント会場や貸し会議室
- ホテル内会議室(安定性重視)
- 専用イベントスペース(都内・主要駅にはいくつかあります)
戦略的に日程や時間を設定する
メディアの編集・制作シフトやサイクルを理解して日程を設定することが重要です。
曜日別の考え方
- 火曜・水曜日:新聞・週刊誌・テレビなど比較的動きやすい曜日。翌日の掲載や放送を狙える。
- 木曜日:翌日金曜日の紙面や朝の情報番組への放送を意識した曜日
- 避けるべき曜日:月曜・金曜日は週初の忙しさ、週末モードで来場メディア数が減少することが多い
時間帯について
- 午前の部(10:00-12:00):午後5時−6時の締切を控えた新聞記者、また午後の情報番組、夕方・夜ニュース番組への放送を狙える
- 午後の部(13:00-15:30):午後の時間帯は様々な取材が入り、新聞は夕方の締め切りもあり忙しい時間帯だが、午後の情報番組での生中継や、その日も夜ニュース番組や翌日の朝の情報番組を対象とするなら良い。
- 競合を回避する: 事前に情報が入るなら、同業他社の発表や大型イベントとの重複を避けることが望ましい。また、政治・経済の重要発表予定日も避けるべきです。
発表会の詳細内容・演出・コンテンツの開発段階(開催3-4週間前)
イベント内容の設計
記者発表会では、シンプルにわかりやすく「新商品」「新サービス」がどういったものなのか?を説明する必要がありますが、見るものを引き付ける構成や演出も大切です。記者発表会において、新商品や新サービスの内容を簡潔かつ明確に伝えることは非常に重要ですが、それだけでは聴衆の心を掴むことはできません。視覚的に魅力的で、記憶に残るような構成や演出を設計することが、発表会の成功には不可欠です。
具体的には、以下の要素を考慮して発表会の内容を設計しましょう。
- ストーリーテリング: 新商品やサービスがどのように生まれ、どのような課題を解決し、どのような未来を創造するのかを、感情に訴えかけるストーリーとして語ることで、製品への共感・理解を深め、記憶に残りやすくなり良い報道露出につながります。
- ゲストスピーカー: 社長や開発者など自社だけの登壇者ではなく、業界の専門家や教授ら、またはイメージキャラクターなどゲストを招き、彼らの視点から製品やサービスの価値を語ってもらうことで、発表内容へのアテンションを獲得することができ、より深い理解と信頼性を与えることができます。
- デモンストレーション: 口頭での説明だけでなく、実際に製品やサービスが動作する様子をデモンストレーションすることで、その機能やメリットを具体的に示すことができます。会場には実際に商品などデモ機を設置して参加者が体験できる機会を設けるのが効果的です。
- ビジュアルコンテンツ:動画、インフォグラフィック、プレゼンテーションスライドなどを活用し、視覚的に情報を伝えることで、理解度を高め、発表会に華やかさを加えます。製品の魅力を最大限に引き出すビジュアルコンテンツを作成しましょう。
- 質疑応答: 発表の最後に質疑応答の時間を設け、参加者からの疑問に丁寧に答えることで、理解を深めるとともに、コミュニケーションを図ることができます。可能であれば、発表会後に製品に触れる機会や、開発者と直接話せる時間を設けることで、参加者の満足度を高めることができます。
これらの要素を組み合わせ、発表会のテーマや目的に合わせて最適なバランスで配置することで、単なる情報伝達の場ではなく、参加者の心に響く感動的な体験を提供できるでしょう。
効果的な発表会のプレゼンテーションとは?
記者発表会でのプレゼンテーションは、よくビジネスの現場で見られるピラミッド構造で組み立てる「結果・結論」から伝えるパターンではありません。(一概には言えませんが)
よくビジネスの場面でみられるピラミッド構造は
- 結論:核心メッセージの明確な提示
- 根拠:データと事実による客観的な裏付け
- 詳細:具体的な説明と事例紹介
ですが、ここは報道関係者や聴衆者を引き付ける演出も重要なのです。かつて、Appleを率いたスティーブ・ジョブズの発表を思い浮かべるといいでしょう。
つまり、聴衆者を惹きつけるために、映画やドラマさながらの構成や演出が必要なのです。
- こんな社会になった、こんな課題がある(背景・社会課題)
- こんな解決方法を取り組んできた、こんな製品が今までもあった(現状の取り組み・製品)
- ただし、それではこんな問題が残っている、こんな課題が解決できない(現状課題)
- そこで我々はこんな商品・サービスを開発した(結論)
- この商品・サービスは今まで解決できなかったこのような課題を解決できる(結論詳細)
- 根拠となるデータや裏付け(エビデンス)
- この商品・サービスで社会をこのように変えていきたい(ビジョンの共有)
- さらに今回はそれだけではありません!実は・・・(サプライズ発表の内容)
8のサプライズ発表はスティーブ・ジョブズの「One more thing・・・」が有名でした。今回の発表はこれだけではないよ、実は本当に発表したかったのはこれなんですよ、と演出により、メディアだけでなく、一般の人たちもグッと惹きつけられ、大きな話題となったのです。
プレゼンテーション内容の補足:視覚的コンテンツの活用
プレゼンテーションはわかりやすいことが最も重要です。「わかりにくい」は客が降りてしまう最大の要因となります。記者が「記事にしたい」と思う視覚的な要素を積極的に取り入れましょう。
- 動画:製品・サービスを魅力的にみせる動画を発表会で流し惹きつける
- Before/After比較:使用前使用後でその効果をわかりやすく可視化する
- インフォグラフィック:複雑なデータを分かりやすいグラフなどで可視化
- タイムライン表示:プロセスの理解促進
ここまでは、開催までに必要な事務的なプロセスを解説しました。
しかし、これらの手順をただこなすだけでは、十分なメディア掲載を得ることは難しいのが実情です。膨大な準備を「成果」に直結させ、記者発表会を本当の意味で成功させるために、特に重要な4つのポイントをご紹介します。
記者発表会を成功させるためのポイント
記者発表会を成功させるためには、ただ準備プロセスをこなすだけではメディア掲載を最大化させることはできません。ここでは成功のために欠かせない4つのポイントを解説します。
1.ニュースバリューの設計
記者が「これは今、報じるべきニュースだ」と判断する基準をニュースバリューと呼びます。単なる自社製品のスペック紹介や新サービスの告知だけでは、広告的な色合いが強くなり、メディアの取材意欲は高まりません。
成功の鍵は、その発表が「現代の社会課題をどう解決するのか」という視点や、「業界初・日本初といった市場へのインパクト」を明確に打ち出すことにあります。例えば、2025年の消費トレンド、SDGs、働き方改革といった世の中の関心事(時流)と自社の情報を掛け合わせる「文脈作り」が重要です。自社の発表を「社会の写し鏡」として位置づけることで、お客様や社会にとっての公共性と優先順位を引き上げます。
2.体験価値の創出
記者発表会は情報伝達の場であると同時に、記者に印象を残す「体験」の場でもあります。
カーツメディアワークスでは特に「情報体験」というキーワードをこの時代に最も重要なことと捉え、「ワクワク」「ドキドキ」「ワオ!」など感情喚起できる発表会を推奨しています。
業界別記者発表会での「情報体験」設計について
ここでは発表会で実施できる各業界別の体験価値の生み出し方について解説していきます。
食品業界:「味覚体験」
- 調理実演と試食
- 開発過程の原材料展示
- 生産地との中継をつなぐ
テクノロジー業界:「未来体験」
- インタラクティブなデモンストレーション/技術の体験
- リアルタイムデータ可視化
- VR/AR技術による没入型体験
ファッション業界:「ブランド体験」
- ブランド世界観の空間演出
- 素材の手触り・試着体験
- デザイナーの創作過程・ドキュメンタリー
美容・コスメ業界:「美的体験」
- 試用・施術体験
- 新施術や成分の勉強会
- 工場見学・プレス見学会など
このように「体験価値」を生み出すことで記者の「もっと取材したい」「書きたい」「放送したい」に応えていくことができます。
試食や試飲、実演やデモンストレーション、プロセスの紹介を通じて「製品・サービス」を紹介し、開発者の表情やこだわりまで伝えることで、より良いコンテンツとなるように「メディア取材のサポートを最大化」するつもりで「情報体験価値」を生み出しましょう。
【関連コラム】
メディア体験会からプレス試食会、工場見学、プレスツアーまで効果的なプレスイベント完全ガイド
https://www.kartz.co.jp/column/detail25/
3.データドリブンな効果測定
記者発表会の成功を一過性で終わらせず、組織の学習資産としてデータの蓄積・活用する仕組みを構築しましょう。
即時効果の測定
- 当日参加記者数と媒体構成
- 発表後、即日の記事数
- リアルタイム反応(SNS言及、質問内容)
短期の成果測定
- 1週間〜2週間以内の掲載記事数と掲載媒体の質
- 記事の論調分析(ポジティブ/ネガティブ/ニュートラル)
- 株価・企業価値への影響(IR視点での分析)
- 使用された写真・映像の種類
- SNS二次拡散状況
中期・長期的な影響評価
- 1ヶ月以上経過してからの報道掲載の分析
- 報道連鎖・波及効果の分析(記者発表会が起点となった他の報道)
- 営業チームへの引き合い増加
4.メディア露出を逆算した演出
テレビ番組やWebニュース、新聞各紙が「そのまま記事や番組に使いやすい素材」をあらかじめ用意しておく戦略です。 特に重要なのがフォトセッションの設計です。登壇者の立ち位置、手持ちパネルのサイズ、企業ロゴが必ず写り込むバックパネルの配置など、メディアのカメラマンが「どこから撮っても様になる」状態を作ります。
また、当日の撮影素材だけに頼らず、高画質な製品画像や補足動画を即座にダウンロードできる環境を整えておくことも欠かせません。Webメディアの速報性を支援し、テレビ局の編集負担を軽減するような「メディアファーストな素材提供」を徹底することで、露出面積の拡大や、意図したブランドイメージでの掲載確率を大幅に高めることができます。
これらのポイントに共通しているのは、自社が伝えたいことだけを一方的に発信するのではなく、メディアの先にいる記者や視聴者・読者が「何を求めているか」という徹底したメディア視点とユーザー視点です。
記者発表会は、多大なリソースを投じる一大イベントです。一過性の打ち上げ花火に終わらせず、ブランドの信頼を中長期的に高める成果を得るためには、こうした戦略的な設計を準備段階から組み込んでおく必要があります。
記者発表会の事例について

「記者発表会」成功事例①:日本酒の体験型記者発表会
企業:地方の老舗酒造メーカー
概要:新商品の高級日本酒の認知度向上と販路拡大
戦略:五感に訴える体験価値の創出
実施内容
- 杜氏による酒造りの実演とこだわりの説明
- 異なる種類の日本酒のテイスティング体験
- 蔵見学と製造工程の詳細説明
- 地元食材を使った料理とのペアリング体験
- 杜氏と参加者の直接対話セッション
成果
- 参加メディア:15人
- 掲載記事・放送:12件
- 発表後の反響:想定の200%以上達成
成功要因
- 実際の製造現場を見学できる貴重な機会を提供
- 日本酒の奥深さを五感で体験できる構成
- 地域の文化や伝統との結びつきを強調
「記者発表会」成功事例②:ドローン・ロボットベンチャーの展示会での発表会
企業:産業用ドローンやロボットの制御システム開発ベンチャー企業
概要:B2B向けドローンや関連システムを使ったサービス、技術力訴求と導入促進
戦略:大型の展示会出展時に合わせ記者発表会を実施。展示会自体への取材来場メディア
に対し、より興味関心を惹くストーリーを発信し事前誘致を実施
実施内容
- 記者が操作しながら説明できるデバイスと設備を用意
- 社長による説明とデモンストレーション
- 他社ブースにはあまりない体験コーナーを設置し画作りに注力
成果
- 参加メディア:23社
- 掲載記事:TV 4番組 新聞・雑誌36件 WEB 170件
成功要因
- 社会課題と絡めたストーリー作りによる事前の情報発信
- 複雑な技術を分かりやすく説明
- 参加者が実際に操作できる体験価値
- 映像メディア向けに画作りができたこと
「記者発表会」成功事例③:CM公開と連動した発表会
企業:大手焼肉チェーン店
概要:大手焼肉チェーン店の新CM、新フェアの話題の最大化による認知向上
戦略:新CM出演タレントの登壇による芸能イベントとしてメディアの関心を最大化
記者への新フェアメニューの試食体験の提供をすることで、芸能+体験要素を付加
実施内容
- CM出演タレントによるトークセッションおよび試食
- 個別インタビューの実施
- 取材来場メディアへの試食提供
成果
- 掲載記事数:300件
- テレビ番組での紹介:5番組
成功要因
- 試食体験機会の提供
- タレント起用による話題化
- 事前の情報設計とメディアリレーションの最大活用
まとめ
記者発表会は、デジタル、AI時代に最も力を入れるべき「情報体験」ソリューションです。戦略的に広報を考え、本記事で紹介したポイントと体系的にアプローチすることで、記者発表会は必ず大きな成果を上げる施策です。
改めて、ポイントを下記に書いておきます。
- 大企業だけのものではない:自社の会議室でも貸し会議室でも記者発表会は成立する。誰でも気軽にできる広報施策が記者発表会です。
- 量も質も重視:参加者数も、掲載記事数(報道数)も、記事や放送の質もどちらも重視する
- ストーリーテリング:単なる情報提供ではなく、記者が記事にしたくなるプレゼンテーション、演出案を生み出す
- 曜日や時間帯:発表会に来てもらいやすく、掲載、放送してもらいやすいスケジュールを設定すること
- データドリブン改善:効果測定と継続的な改善サイクルを確立する
当社、カーツメディアワークスは、継続的に「記者発表会」の改善と深化を追求し、今までにない新しい「情報体験」を生み出していきます。ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。
広報・PRでお悩みの方必見!
お役立ち資料一覧
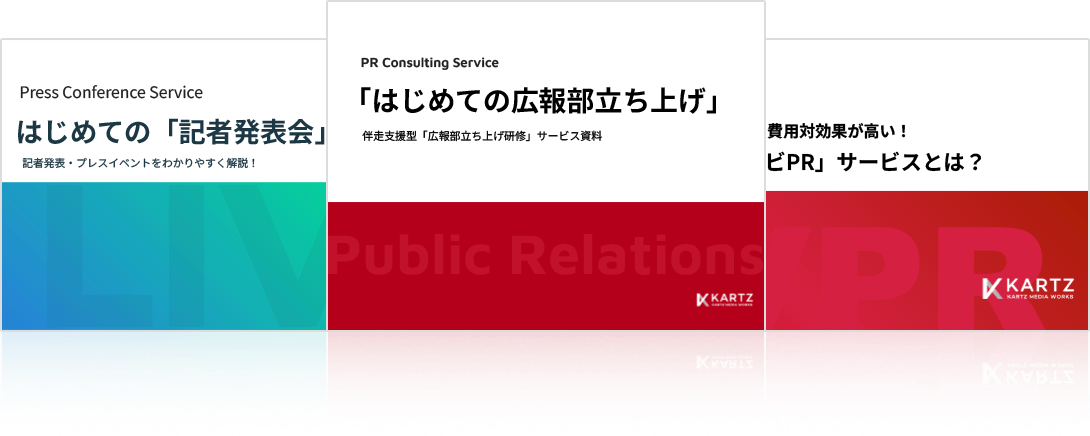
- 広報部を立ち上げたいが進め方が分からない
- 新サービスをテレビに取り上げられたい
- 海外でのPR戦略を構築してほしい
上記のようなお悩み
ありませんか?
カーツでは、上記のようなお悩みを解決する
ダウンロード資料をご提供しております。
是非、ご覧ください。
著者