ジャーナリスト対応で知っておくべき9つのポイント

ピッチ上手になるためには、やはりメディア担当者とのポジティブな関係性を時間をかけて築き上げることが大切です。ここではどうすればこのようなプライスレスなコネクションを育むことができるのかについて、9つのポイントをご紹介していきましょう。
①インタビュー前に準備時間を確保する
ジャーナリストからの電話取材では、即答を求められることもありますが、速報ニュースであるか、あるいは事前にきちんと準備ができている場合をのぞいて、少し間を置いて、あとですぐに掛け直すと提案しましょう。こうすることできちんと対応することができます。
電話を切る前に少し時間をもらって、ジャーナリストに逆に質問をしたり、記事でフォーカスしたい内容やなぜ自分が適任と考えているのかについて質問をしておきましょう。自分以外にもインタビューをする人物がいるのか、電話をかけ直す前に調べておくべき内容はあるのかについても確認をしておきます。あとはインタビューの準備ができたところで電話を掛け直せばいいのです。
②デッドラインを知る
ジャーナリストに掛け直す際にはギリギリまで待たせないように気をつけましょう。ジャーナリストは納期に追われて忙しくしており、デッドライン間際になってしまった場合、おそらくすでに記事のほとんどが書かれた状態になっているでしょう。こうなるとせいぜい一つか二つのコメントを付け加えてもらえる程度。適切なタイミングで対応をすることができれば、記事全体の論旨に影響を与えることができ、ジャーナリストに視点の広がりをもたらし、記事内容に新たな切り口を加えることも可能です。
③決して「ノーコメント」と言わない
このフレーズほど非常に不利ものはありません。こう言わざるを得ないということは、以下のどれかだと考えられます:
- 考えをまとめているところである。
- 回答を持ち合わせていない。
- センシティブな内容であり、さらなる検討が必要である。
- その質問に答えたくない。
「ノーコメント」は、たとえ正当な理由があっても、「なにかを隠している」と誤解されやすい言葉です。
なにも秘密を開示しろと言っているのではありません。計画を立て、回答を用意し、適切に回答することが肝要です。
④オフレコの会話を避ける
秘密は隠しておくのが難しいもの。ジャーナリズムにおいては、「機密性」というコンセプトは”オフレコ”扱いのトピックとして知られていますが、なかなか厄介なものです。“オフレコ”の解釈は報道機関や記者ごとに異なり、共通のルールが存在しません。ジャーナリストが秘密のままにしておくというのは難しいと考えておきましょう。そのため、基本的にはオフレコの会話は避けるべきです。万が一オフレコの会話をするのに同意する場合は、以下を押さえておいてください。
- 事前に報道のプロに相談する。
- ジャーナリストとの履歴を振り返って問題がないかを確認する。
- ジャーナリストに「オフレコ」の定義を確認しておく。
- 会話を始める”前”に合意を取り付けておく。
⑤事前に質問を入手する
メジャーな新聞社などは事前に質問を提供することに同意してくれないものと考えておくべきですが、専門性の高い業界誌や、エンターテインメント系の報道組織などの場合には事前に質問を共有してもらえる場合があります。
しかし、インタビューは「なまもの」でもあります。話の流れで新たな質問が出てくることもありますので、きちんと準備をしておきましょう。特定の情報やデータが必要かを事前に確認しておくことで、より適切に備えることができます。
⑥時計に目をやる
インタビューの時間は、事前に適切な範囲で設定しておくことが大切です。限られた時間内で効果的に情報提供を行うことで、取材対応の質も上がります。また、終了時間が近づいた際に円滑に話をまとめられるよう、事前に要点を整理し、終了のタイミングを明確にする準備もおすすめです。
⑦インタビューを録音する
多くのジャーナリストは純粋に正確かつ説得力のある記事を書こうとしているにもかかわらず、インタビューの内容について間違った引用をしてしまうこともあります。そこで、インタビューの前に会話を録音したい旨をきちんと伝えて、合法的に録音をしておくといいでしょう。
⑧無理にすべての質問に答えようとしない
インタビューされる人の多くは、(特にプレッシャーの多いインタビューでは)すべての質問に答えなければと考えるもの。もし脱線した質問や自分の専門とかけ離れた質問が投げかけられた場合、無理に答える必要はありません。無理に答えようとせず、回答を控えたり、必要に応じて社内の専門担当者を紹介するなど、誠実な対応に努めましょう。曖昧な回答は誤解や誤報を招くリスクにもつながるため、明確に線引きをすることも重要です。
⑨ファクトチェックへの協力姿勢を示す
記事の内容そのものを見せてもらうことは一般的には難しいものの、引用や数値データ、専門用語などの正確性を確認する意図で「ファクトチェック」を求められることはあります。これは記事のリライトを求めるものではなく、事実の明確化や補足を目的とした建設的なやり取りです。意図を尊重しつつ、情報の正確性に貢献できるよう心がけましょう。
広報・PRでお悩みの方必見!
お役立ち資料一覧
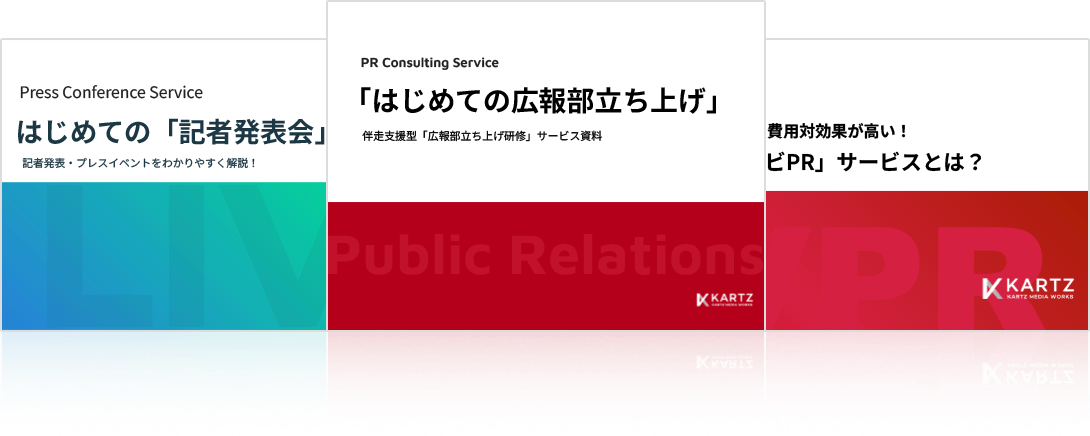
- 広報部を立ち上げたいが進め方が分からない
- 新サービスをテレビに取り上げられたい
- 海外でのPR戦略を構築してほしい
上記のようなお悩み
ありませんか?
カーツでは、上記のようなお悩みを解決する
ダウンロード資料をご提供しております。
是非、ご覧ください。
著者

株式会社カーツメディアワークス
PR事業部 戦略PR局執行役員
森山 稚夏
実績
- コスメブランドの広報戦略・施策実行
- 国内BtoB上場企業の広報戦略支援/記者発表会 企画・運営
- 有名飲食チェーンの広報戦略・施策実行
等多数



